日本銀行が進めている中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証実験が、2023年4月から国内大手行と強力して「パイロット実験」を実施することになったと2月17日に発表されました。
法定通貨がデジタル化されれば、現金ではなくデジタル円でスマートフォンのアプリなどを通して、給料を手にして、消費や投資を行うことができます。
なお日本では、CBDCを導入するかは、現時点では決まっておらず、日銀では「今後の国民的な議論の中で決定するべきもの」との考えです。
今回は、実証実験が始まるこの日銀のデジタル円について解説します。
目次
デジタル円の実証実験始まる
冒頭でお話しした通り、日本銀行は4月から中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証実験が始まり複数年にわたり行われます。
銀行の勘定系システムなどと接続し、入出金や送金に支障がないか検証します。
4月からのパイロット実験には、メガバンクや地方銀行、数十社にもおよぶキャッシュレス事業者も参加し、デジタル円発行に向けた取り組みは新たな局面に突入します。
中央銀行デジタル通貨とは?

中央銀行デジタル通貨は英語でCentral Bank Digital Currencyと呼ばれ「CBDC」と略されます。
中央銀行デジタル通貨は以下の3点の条件を満たすものとされています。
- デジタル化されていること
- 円をはじめとした法定通貨建てであること
- 中央銀行の債務として発行されること
中央銀行は、誰でも1年365日24時間使用できる支払い決算の手段として銀行券を発行していますが、これをデジタル化できないかという議論があります。
実際に具体的な検討に入っている国もあります。
しかし、民間銀行における預金や、資金仲介への影響など、問題点も多く日本をはじめとする主要国の中央銀行は慎重です。
デジタル円の仕組み
デジタル円とは、日本の中央銀行が発行する、デジタル化された法定通貨です。
デジタル化されているので、紙幣は電子化され、主にネット上で発行・流通されます。
日銀は、21年以降2段階に分けてデジタル円の検証を行いました。
その上で、23年4月からは実際の利用を想定した実証実験を行います。
大きな目的は、デジタル時代にふさわしい決済制度を作り上げることです。
スマートフォンの普及によって、全世界的にモバイル決済などの新しい決済方式が増えました。
従来の現金での経済運営であれば、利用者はスマホのアプリにお金を入れてチャージし決済を行います。
しかし、それには手数料が発生します。
一方で、法定通貨がデジタル化すれば、デジタル円でスマホのアプリなどを通じて給料を受け取り、消費や投資を行うことが可能です。
中央銀行デジタル通貨の課題
日本銀行が発行に向けて研究しているものが、中央銀行デジタル通貨(CBDC)です。
従来のデジタル通貨は、法定通貨をデジタル化したものですが、CBDCは、法定通貨自体を電子的に発行します。
極論を申し上げれば、完全にCBDCに移行すると、銀行など金融機関の普通預金は必要なくなります。
しかし、CBDCはそんなに簡単に発行できるものではありません。
日本銀行はCBDCの課題として。以下の点を挙げています。
- 特定の端末やカードの依存を減らし誰でも使えること
- 偽造紙幣の防止および同様の偽造耐性が必要
- 24時間365日、災害時であっても使用できる強靭性が必要
- 速やかに決済を完了させるシステム性能および拡張性が必要
- 民間の決済手段と相互に運用できることが必要
参照:「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針」の公表について
ここまでの取り組み
日銀は21年4月、実証実験の「フェーズ1」をスタートしました。
フェーズ1では、システムの基盤ともいえる「CBDC台帳」を中心に考え実験環境を構築し、発行や払出をはじめとする基本的な取引を的確に処理できるかの検証を行いました。
その後22年4月、「フェーズ2」へ移行し、CBDCにさまざまな周辺機能を付加し、実現可能性や課題を検証しています。
デジタル通貨と電子マネーや仮想通貨の違い
電子マネーは一見するとCBDCに似ていますが、あくまでも決済業者が管理しているデータです。
使用可能な店舗は、その業者と契約している店舗のみです。
基本的には、他の電子マネーに交換することも不可能ですし、残高を現金化することも難しいです。
また、代金を電子マネーで受け取った店舗は、その現金の入金を1ヶ月〜2ヶ月待たねばなりません。仮想通貨は民間業者が発行する「プライベートデジタル通貨」です。
仮想通貨の代表的な「ビットコイン」や「リップル」などは、国家による裏付けのような資産がないので、価値の変動が大きいのが特徴です。
一方のCBDCは各国の中央銀行が発行するデジタル通貨です。
価値は法定通貨と完全に一致し、現在の現金と同様の感覚で決済に使用できます。
CBDCのメリット

ここからは、CBDCを活用するメリット3点を紹介します。
コストの削減
このコストの削減とは主に現金に関することです。
現金は紙で発行されているので、作成にはじまり、保管や輸送、警備に至るまでさまざまなコストがかかっています。
店舗に設置されているレジや銀行のATMなど現金を扱っているものは、世の中に多くあります。
CBDCが一般化すれば、現金の取引は減少するので、コストの低下が期待できます。
マネーロンダリングの防止
CBDCは、デジタルデータなので、入出金の流れが一目瞭然です。
マネーロンダリングや脱税などを防ぐことができ、税収入が増える可能性もあります。
利用者の目線で考えても、収入や支出などのお金の流れがすべて記録に残るので、納税の手続きが少なくなります。
ファイナンシャル・インクルージョンの推進
ファイナンシャル。インクルージョンとはあまり聞き慣れない言葉かもしれません。
日本語にすると「金融包摂」で、「経済活動に必要な金融サービスを、貧困層や僻地に暮らす人々など誰でも利用できること」です。
発展途上国などでは、利便性の低い決済手段しかなかったため、経済や社会発展が遅れているところも多いのです。
CBDCによってファイナンシャル・インクルージョンが進めば、たとえ銀行口座を持っていなくても、金融サービスの普及が期待できます。
CBDCのデメリット
もちろんCBDCはいいことばかりではなく、デメリットも存在します。
ここからはCBDCのデメリットについて解説します。
セキュリティ問題
CBDCに限らずデジタル通貨は、クラッキングやハッキングの対象になりやすく、法定通貨建てのデジタル通貨であれば、最高クラスのセキュリティが必要です。
そのため、高度の技術や高額な維持費が必要になります。
さらに近年は、キャッシュレス決済のトラブルは増加傾向にあります。
災害時のリスクの問題
災害時のリスクが大きい点もデジタル通貨のデメリットです。
デジタル通貨は、デジタル上で展開されるので、災害時などにネットワークの不具合が発生すると、機能停止の恐れがあります。
そのため、オフラインでも使用可能な仕組みを作ったり、強固なセキュリティ基盤を整えたりするなどが必要です。
まとめ
現在の電子マネーサービスとの関係や、発行額や保有額の制限、海外送金・決済対応、セキュリティなど考慮しなくてはならないポイントはさまざまあります。
日銀は仮にデジタル円が導入されても、需要がある限りは紙幣を発行し続けるスタンスなので、急に現金がなくなることはありません。
また、金融機関では、通貨のデジタル化がすすむ中、紙文書だけでなく電子文書の管理も必要です。
効果的に電子文書を管理したい場合は、SRIの「BUNTANリーガル」にお任せください。
WEBシステムの「BUNTAN」にデータベース化し、電子文書の検索や期限管理はもちろん、文書原本の保管から廃棄までのライフサイクルやPDFなどの電子データまで一元管理いたします。
文書の保管方法にお悩みの企業様はぜひ一度SRIにご相談ください。
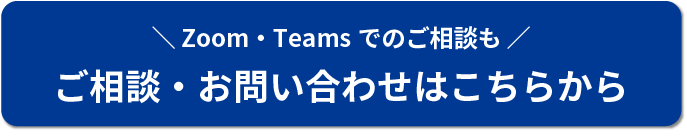

 お問い合わせ
お問い合わせ
 資料請求
資料請求

